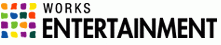「人的資本経営」を支援することでそれぞれ個人と組織が働きやすく 働きがいのある社会を創ることが当社のミッションです。
提供サービス

個性データとストレス値の可視化が可能なのはFFS理論のユニークさの最大の特長です。「この人を採用したらチームの個性はどう変わるか」「Aさんをこのチームのマネージャーにしたら、部署がどう動くか」「コミュニケーションミスが頻発するのはなぜか」を解決してみたいと思いませんか

「トップセールスをマネージャーにしたのに」「スペシャリストをどうマネジメントすればいいのか」こうした悩みをもつ経営者や人事部の方々はおおく、マネージャー自身も悩んでいます。FFS理論導入で社内共通言語になると、この悩みが驚くほど解決できます。

FFS理論は「ストレスと性格」の研究において開発された理論です。そのためストレスマネジメントにも活用できます。ストレス=外的刺激にどう自己が反応するかを学び、日常業務においてどうストレスを向き合うかをワークショップを通して学ぶことができます。

自己理解・他者理解が進むと「自分のチームは、こうやったほうが仕事が進むのではないか」「目標設定は個別対応したほうがいいのではないか」と改善案が次々と浮かびます。もちろん社外のお取引先とのコミュニケーションにも活かすことができます。チーム編成、活性化をどうしようかという悩みも人と人の組み合わせをカガクすることでサポートできます。
FFS理論の提唱者
小林 惠智(こばやし けいち)氏
組織心理学者・教育学博士、経済学博士である小林惠智氏によって提唱されています。
1950年生まれ。国際基督教大学を経て、ウィーン大学基礎総合学部哲学専修科(修士課程)修了。モントリオール大学国際ストレス研究所で専門研究員。ストレス学説創始者ハンス・セリエ博士のもとで「ストレスと性格特性」に関する研究に従事。フロリダ州立大学社会心理学研究室で実験心理学を専修。教育学博士。ノースウェスタン大学組織経済学研究室、組織および教育経済学研究および客員教授。経済学博士。米国・国際戦略研究所 組織戦略・組織編制専門研究員として「最適組織編成プロジェクト」に参加しFFS理論(最適組織編成の為の個性分析と組織編成法)を提唱した。日本においてCDIヒューマンロジック研究所を設立し事業継続と人事システム設計、企業組織の活性化、組織経営コンサルタントの育成および国内の大学・大学院の特別講義講師を歴任。現在に至る。
株式会社ヒューマンロジック研究所より