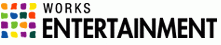ときおり「モチベーションをあげるにはどうしたらいいですか」といった趣旨のご相談をいただくことがあります。そこで私がいつもお答えしている内容をまとめました。
― ストレスマネジメントで“やる気”を整える方法 ―
「最近どうもやる気が出ない」
「メンバーのモチベーションが上がらない」
「モチベーションスイッチってどこ?」
SNSでも“やる気を出す方法”がよく流れていますよね。
でも、脳科学的にいえば――“モチベーションを上げる”という発想そのものがまちがいです。
モチベーションは“上げる”ものではなく、“整える”もの
脳の中で「やる気」を生み出すのは、ドーパミンという神経伝達物質。「快適なとき」や「報酬を得たとき」だけでなく、「できた!」という小さな達成でも分泌されます。
つまり、やる気が出たから動くのではなく、動いた結果やる気が出る。
これが脳の仕組みです。
脳の報酬系は“行動のあと”に反応します。
たとえば、
- メールを一通送れた
- タスクがひとつ終わった
- 誰かに「ありがとう」と言われた
こうした些細なことでも、脳は「進んでいる」と感じてドーパミンを出します。
この「快」のサイクルが回り出すと、自然とエネルギーが湧いてくる。
これが、私たちが“モチベーション”と呼んでいるものです。
だから“メンバーのやる気を上げよう”とするよりも、
【行動を始めやすくする環境を整える】ことが何より大事です。正直、「上げよう」として懇親会開催するとか、話し合うとかは期待するほどの効果はなさそうです。1on1も、いまやただの業務ミーティングになってますしね。
戦略とは環境を整えること。
戦術は環境の中でどう展開していくか。
作戦は展開の具体的なタスク。
まさにこの考え方が的を射ています。
ストレスとモチベーションは、同じネットワークを使っている
意外と知られていませんが、ストレス反応とモチベーションは脳内の同じ回路を通っています。
過度なストレスがかかると、扁桃体が過剰に働き、冷静な判断や計画を担う前頭前野の働きが鈍くなります。
この状態では、
- 注意が散る
- 判断力が落ちる
- 「やる気が出ない」と感じる
といった現象が起こります。
つまり、やる気が出ない=ストレス過多で脳が防御モードに入っている状態。
だから、やる気を“上げる”という試みや、期待どおりに動かない相手に対して「怒る・叱る・詰め寄る」といった行動よりも、まずは脳の安全装置を解除することが最優先です。
脳を整える=ストレスをマネジメントすること
脳を整えるために必要なのは、脳のメンテナンスです。
次のような行動が、ストレスを下げてドーパミンの循環を回復させます。
- よく眠る
睡眠不足は扁桃体の興奮を高め、ネガティブ思考を強めます。
まずは7時間を目安に、睡眠の質を確保することが重要です。
入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒はディストレス(悪いストレス)のサインです。 - 体を動かす
軽い運動でセロトニンが増え、ストレスホルモン(コルチゾール)が減少します。
1日20分のウォーキングでも効果があります。
「仕事で歩き回っているから大丈夫」と言う人もいますが、それとは別で“意図的に動く時間”を。 - 感情を言葉にする
モヤモヤを言語化すると、前頭前野が働いて扁桃体の暴走を抑えます。
言葉にならない段階の“身体反応”は「情動」と呼ばれます(好悪/快不快/危険)。
「なんとなく好き」「疲れた」「イライラしてる」など、
まず“名前をつける”だけでもOK。手書きメモならより効果的です。 - 安心して話せる場を持つ
オキシトシン(安心ホルモン)が分泌されると、ストレス反応が沈静化。
雑談や共感の時間も、立派なストレスケアになります。
マネジメントができる3つの設計
チームや部下のモチベーションを“上げよう”とするより、自然にドーパミンが出る仕組みをデザインしましょう。脳=心なので、理にかなったマネジメントです。(ここは次回またブログ書きます)
① 小さな達成を可視化する
「進んでいる実感」は誰にとっても最大のやる気スイッチ。KPIでも日報でも構いません。
“進捗が見える”だけで、脳は報酬を感じます。逆に見えないと、ネガティブストレスが溜まり、
期待とのギャップから言動が荒くなりやすくなります。
② 安心のベースをつくる
過度な緊張や叱責は、扁桃体を過敏にして行動を止めます。
心理的安全性は、やる気のベースとなる「脳の安全空間」です。
③ 承認より共感を
「よくやったね」よりも「大変だったね」「工夫してたね」。結果よりプロセスへの共感が、オキシトシンを生み、信頼と挑戦意欲の両方を伸ばします。
わたしはつい「で、結果は?」と言ってしまいがちです…
結論:モチベーションとは“脳の状態管理”
やる気を出すコツを探すより、脳が自然に動ける状態を整えるほうが、チームにはずっと効果的です。
ストレスを把握し、睡眠・栄養・人間関係を整えれば、脳は勝手に動き出します。その流れの中で「モチベーションが上がった」と感じるのです。
だから、マネジメントに必要なのは「励ます力」ではなく、環境をデザインする力。
社員一人ひとりが安心して挑戦できる土台を整えれば、
やる気は“与えられるもの”から“内側から湧き出すもの”へ変わります。
モチベーションをあげたいと思ったら、まず整える。
それが、脳が力を引き出すいちばんの近道です。
まとめ
- モチベーションは“上げる”より“整える”
- 行動のあとにドーパミンが出る(行動→やる気)
- ストレス過多だと扁桃体が過剰反応してやる気が止まる
- 睡眠・運動・共感がドーパミンとオキシトシンを整える
- マネージャーの役割は「環境をつくること」