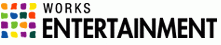新卒・中途・同僚・友人・スポーツ..「がんばれ!!」って言うこと多いですよね。
じつは私は…このセリフを言うのも、言われるのも、すばらしく苦手です。
「がんばれ!」と言われるとですね、脳内で
「え、これ以上、なにを?」「いま頑張ってないとでも?」という黒めのセリフが浮かびます。また声がけするときは「みんな頑張っているしな」というニュアンスのストッパーが作動しています。
「なんでだろう」と思っていたのですが、結論から言うと、「『頑張れ!』という声かけ=必ずしも、脳/動機づけ的に最善とは言えない」という見解が、教育・心理・神経科学の研究から出ていました。
「絶対にダメ」というわけではなく、どう言うか・何に焦点を当てるかがポイントだそうです
複雑なようでシンプルな脳
「君は頭がいいね」「すごい才能だね」と、能力や結果そのものを褒めると、困難に直面した際に「私はもうできないかもしれない」と諦めやすくなるという傾向があります。
一方で「よく考えたね」「この戦略が良かったね」「努力の跡が見えるね」など努力・プロセス・戦略に焦点をあてた声かけは、挑戦を続ける姿勢(=レジリエンス)を育てやすいという研究もあります。
「がんばれ!」という言葉は、能力・結果どちらか曖昧なものとして脳はうけとり、むしろ「何が良かったのか?」を内省しづらく、自己判断・メタ認知の育成を阻害する可能性が指摘されています。良かったときも悪かったときも要因を把握しようというのがこれです。
ちなみにみんな大好きな「原因」は探しても無意味です。因果関係は複雑すぎて真因にたどり着くのに時間がかかりすぎるので、要因をさがし相関関係を把握するほうが実利あります。そもそも脳の数だけ事実があるので、原因探しをすると、話がまとまりません。
「がんばったね」という褒め言葉をきくと、脳の報酬系(側坐核/ドーパミン系)が
「期待」→「達成」の過程で反応します。「褒められた/結果が良かった」というだけでは、
この“プロセスを通じて得た達成感・学び”の回路を育てづらいのだそうです。
また、声かけが「(君がもっと)がんばれ!」という漠然とした命令や期待だと、受け手の脳は「プレッシャー/期待されている」というストレス信号を受け取ることもあります。
ここに“やらされ感”が高まると、脳の実行機能(前頭前野)に余裕がなくなりやすいという指摘があります。
まとめると声かけで「がんばれ!」だけを投げると、受け手は“何をどう頑張ればいいのか”“その先どうなるのか”が曖昧になり「ただ頑張らなきゃ」というプレッシャーになる可能性あり、眼の前のことにのみフォーカスしがちです。
一方で、「努力を認める」「手順や戦略・戦術・作戦を言語化しつたえる」「次にどうすればいいか提案する」などの声かけは、脳のプロセス回路・自己効力感回路に好影響を与える可能性あります。
「頑張れ」という“声かけ=頑張れ”がすべてダメというわけではありません。
状況・受け手・声かけのタイミングや内容によって、効果が変わります。例えば:
緊急の場面で士気を上げるために「頑張れ!」と声をかけるのは、短期的な覚醒効果を持つことがあります。(とはいえ協調性を刺激するため、そうではない因子の人には逆効果です)
ただし、先にかいたとおり、その後の振り返り・意味づけ・次のアクション設計がないと、
長期的な成長・習慣化にはつながりにくいです。
成長を目的とする研修・教育・人材育成のコンテクストでは
1.なぜ頑張るのか
2.どう頑張るのか
3.次にどうするか
の三点が明確な声かけの方が効果的ですし、さいごに
4.その結果どこを目指しているのか
5.どういう状態になるのか
まで明示するとなお良いそうです。
研修テキスト・マネジメント現場で使える、脳的に効果的な声かけを下記に整理します。
・「頑張れ」→「〇〇のこの部分、やってくれたの嬉しかった/助かったよ。次は△△を意識してみよう」
・「よくやった!」→「このタスク、君が△△を工夫してくれたおかげでスムーズに進んだ。
特に□□の判断が良かった。次もその調子で、でも△△をさらにこうしてみよう」
・「もっと頑張ってね」→「次のチャレンジとして、□□をどう工夫するか一緒に考えよう。どんな選択肢があると思う?」
声かけの中で意図的に入れたい要素は:
・具体的な行動・戦略に言及する。
・次にどうするか・改善策を併記する。
・本人がコントロールできる領域(努力・工夫)に焦点をあてる。
です。ちょっと心がけてみてはいかがでしょうか。